顎関節症を患っている方は、これまでのように日常生活を送ることができず、日々辛い思いをしていることでしょう。
そのようなときは、自身の状態に合わせたセルフケアにより、少しでも症状が良くなるように努めてください。
ここからは、具体的なセルフケアの方法を中心に解説したいと思います。
●症状が強いときのセルフケア
顎の痛みや開口障害、開咬時の異音など、顎関節症の症状が強い場合は、まずよく噛まなければいけないようなものを避けます。
フランスパンのように、一見やわらかそうであっても、噛み切りにくいものは顎に負担をかけるためNGです。
野菜や果物については、調理時になるべく小さめに切るようにしましょう。
また、症状が強い場合は、とにかく顎に負担をかけないように気を付ける必要があります。
例えば、あくびをすると急に口が大きく開き、顎に過度の負担がかかります。
かといって、無理に抑えるのは難しいため、あくびをしたくなったときは、下顎の下に手を添えて、口が開きすぎないように軽く押さえると良いでしょう。
●比較的症状が落ち着いているときのセルフケア
顎関節症の症状が落ち着いている場合は、顎関節症に効果的な運動療法をセルフケアとして取り入れてみましょう。
こちらは、開口訓練と呼ばれるもので、具体的には口を大きく10回程度開ける練習をするというものです。
この時、手の指を顎骨のところに軽く添え、ゆっくりと大きく口を開けるのがポイントです。
また、開口訓練は、1日10分程度、毎日継続して行うことで効果を発揮します。
習慣づけられるように、入浴時や就寝前に行うようにしましょう。
●セルフケアで症状が改善しない場合
セルフケアで顎関節症の症状が一切改善しない場合は、歯科クリニックを訪れ、ナイトガードなどの治療を受けなければいけません。
ナイトガードは、顎関節症の治療としてもっともポピュラーであり、就寝時に装着することで、歯ぎしりや食いしばりによる負担が分散され、顎関節も守ってくれます。
また、ナイトガードは噛み合わせの不具合を調整することができるため、本来の噛み合わせになるように不具合を調整し、顎関節にかかる負担も減らす効果が期待できます。
●この記事のおさらい
今回の記事のポイントは以下になります。
・顎関節症の症状が強いときは、とにかく顎に負担をかけないことが大切
・あくびをするときは、下顎の下に手を添えて、口が開きすぎないようにする
・症状が落ち着いているときは、セルフケアとして開口訓練を行うのがおすすめ
・セルフケアで改善しない場合はナイトガードなどの治療を受けるべき
以上のポイントはしっかりと押さえておきましょう!
新潟市西区周辺やJR越後線「寺尾駅」付近で歯科クリニック(歯医者さん)をお探しの方は、是非、ひらの歯科医院へお問い合わせ下さい!
万全の感染予防対策でお待ちしております。






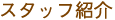

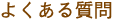
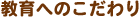
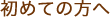




















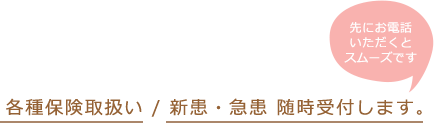

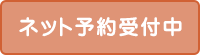
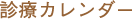






 TEL
TEL