歯が痛む疾患と聞いたとき、ほとんどの方は虫歯を思い浮かべるでしょう。
しかし、実際は他にも歯が痛む疾患は存在します。
こちらは、歯が原因ではない歯痛ということで、非歯原性歯痛と呼ばれています。
今回は、虫歯と非歯原性歯痛の主な違いについて解説します。
原因について
虫歯と非歯原性歯痛における違いとしては、まず原因が挙げられます。
虫歯の痛みについては、主にミュータンス菌などの虫歯菌によって引き起こされます。
その他歯周病菌や歯のヒビなど、歯もしくはその周辺組織が原因で生じるものについては、虫歯に該当します。
一方、非歯原性歯痛は筋肉や神経、鼻や心臓、ストレスなど歯以外の部分が原因で起こる歯痛です。
具体的には咀嚼筋の凝りや副鼻腔炎、偏頭痛や狭心症の前兆などによる痛みを指しています。
虫歯は痛む歯を特定できることが多いですが、非歯原性歯痛は範囲が広かったり、日によって痛む場所が変わったりするため、非常に厄介です。
刺激による反応
虫歯と非歯原性歯痛とでは、刺激による反応も異なります。
虫歯は基本的に、冷たいものを口に入れたときにズキッとした痛みが走ります。
ある程度進行している場合は熱いものもしみるようになり、叩いたときに響いて痛むこともあります。
一方、非歯原性歯痛は、特定の動作を行ったときに痛むというケースが多いです。
例えば歩いたとき、口を大きく開けたとき、頭を振ったときなどに痛みが生じるため、口内を刺激されて痛みが出る虫歯とはかなり仕組みが違うと言えます。
その他の違い
虫歯と非歯原性歯痛におけるその他の違いとしては、麻酔の効果や検査時の特徴などが挙げられます。
虫歯による痛みは、歯科クリニックの麻酔でピタッと止まります。
一方、非歯原性歯痛については、麻酔をしても基本的には痛みが消えません。
また歯が痛むとき、多くの方は歯科クリニックで検査を受けるかと思いますが、虫歯の場合はレントゲン検査を受けたとき、異常が見つかります。
これに対し、非歯原性歯痛は歯が原因ではないため、レントゲン等で検査をしてもこれといった異常が見つかりません。
この記事のおさらい
今回の記事のポイントは以下になります。
・歯が原因ではない歯痛は非歯原性歯痛と呼ばれる
・虫歯は主に歯が原因、歯原性歯痛は筋肉や神経、ストレスなどが原因で発症する
・刺激による反応も、虫歯と非歯原性歯痛とでは大きく異なる
・虫歯は麻酔で痛みが止まるものの、非歯原性歯痛は止まらない
・非歯原性歯痛は、レントゲン検査を行っても異常が見つからない
以上のポイントはしっかりと押さえておきましょう!
新潟市西区周辺やJR越後線「寺尾駅」付近で歯科クリニック(歯医者さん)をお探しの方は、是非、ひらの歯科医院へお問い合わせ下さい!
万全の感染予防対策でお待ちしております。






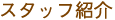

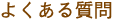
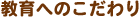
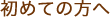






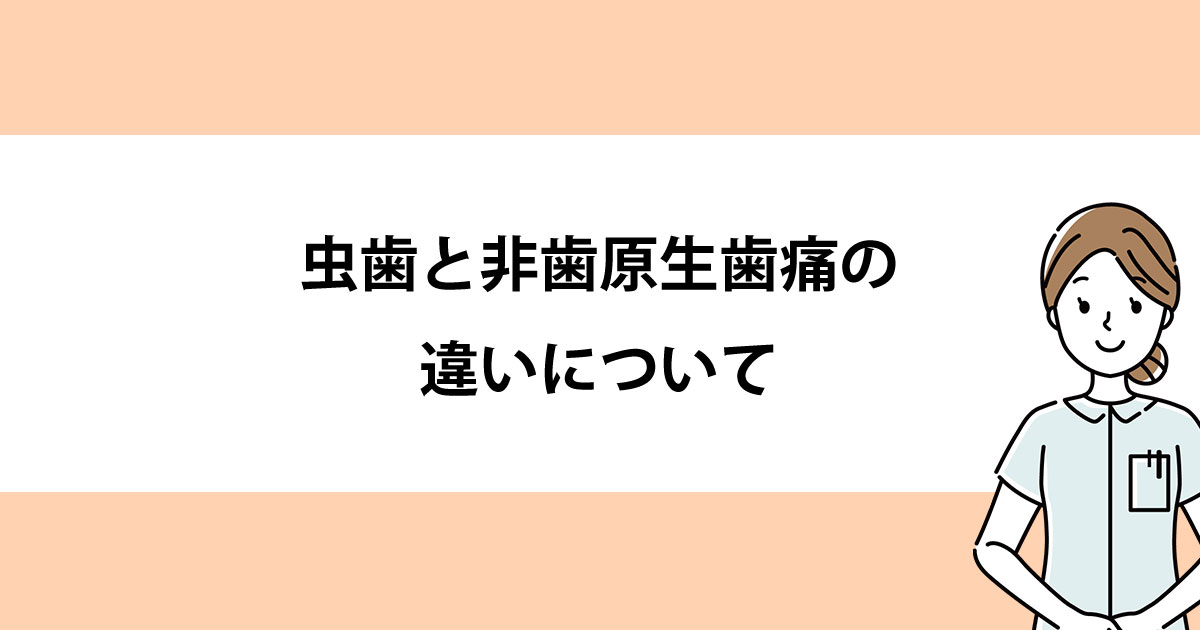
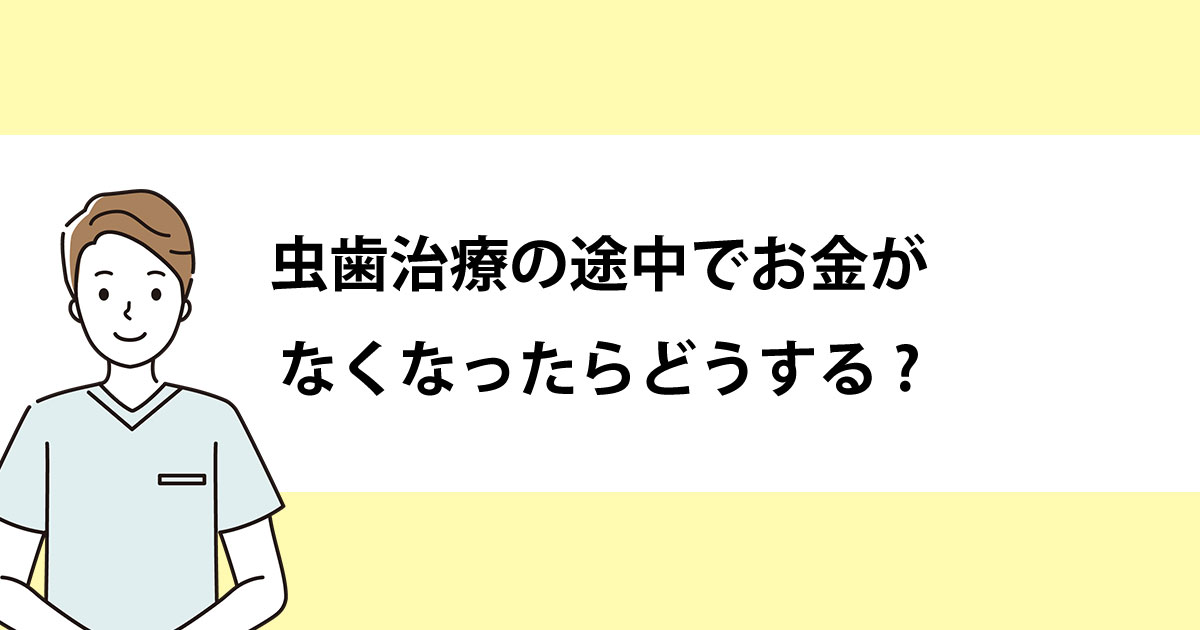
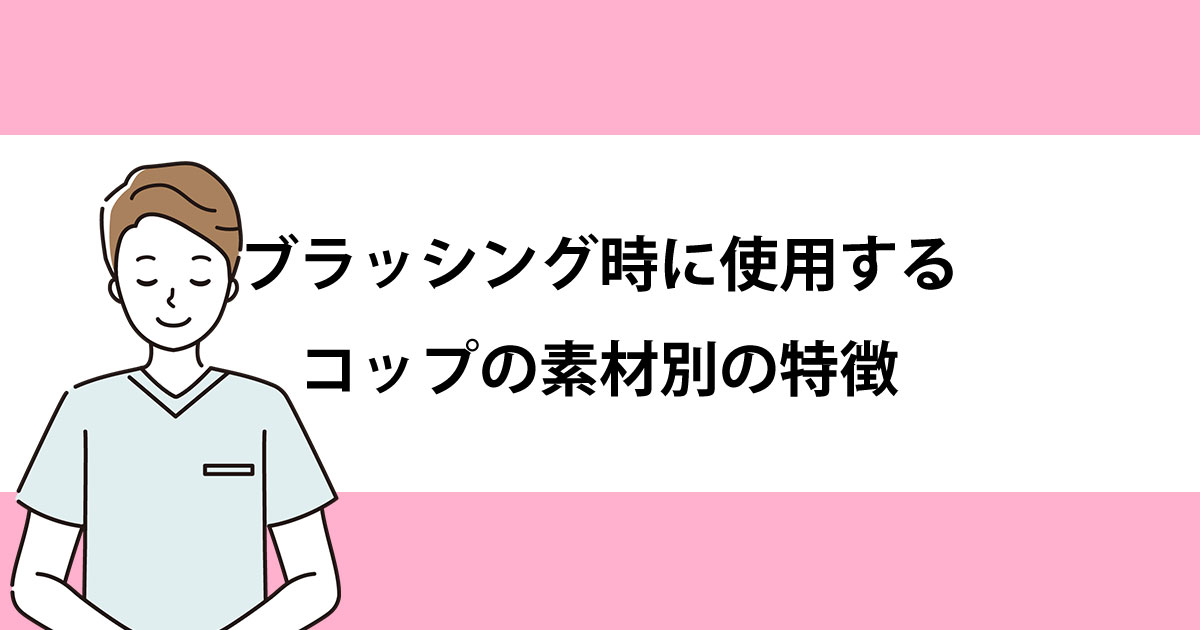
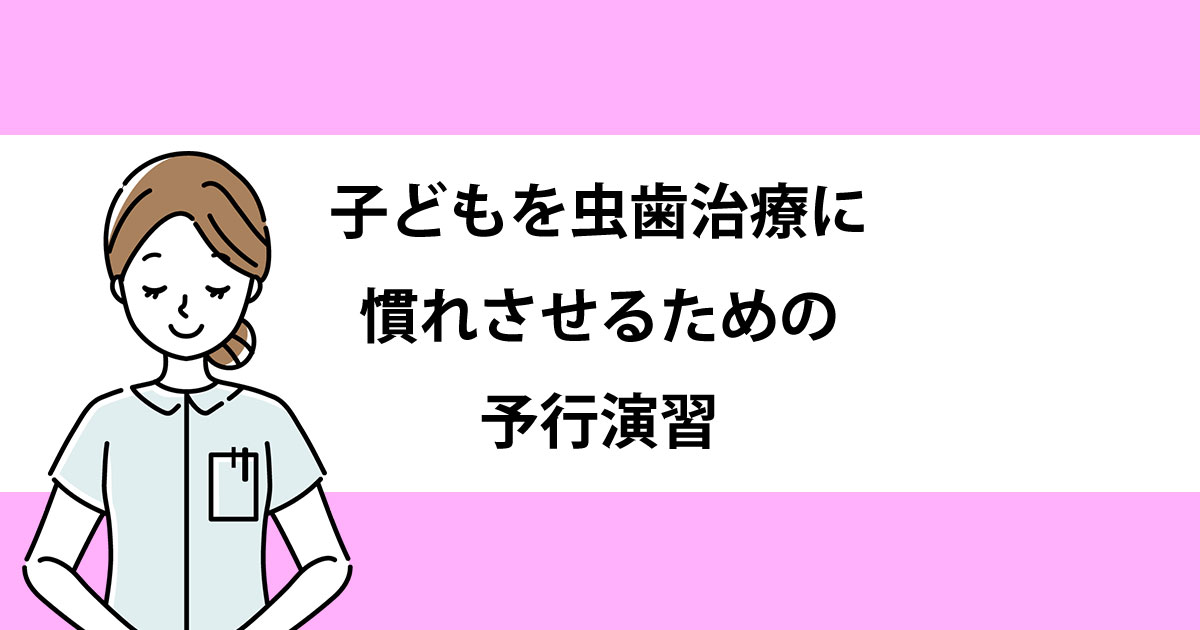
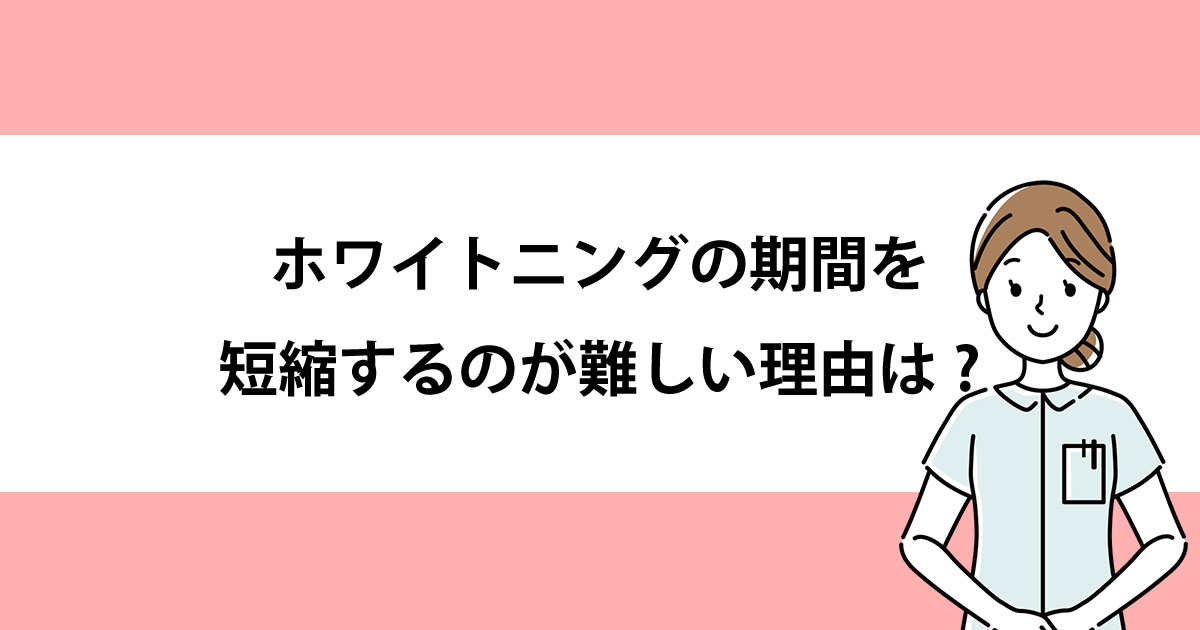
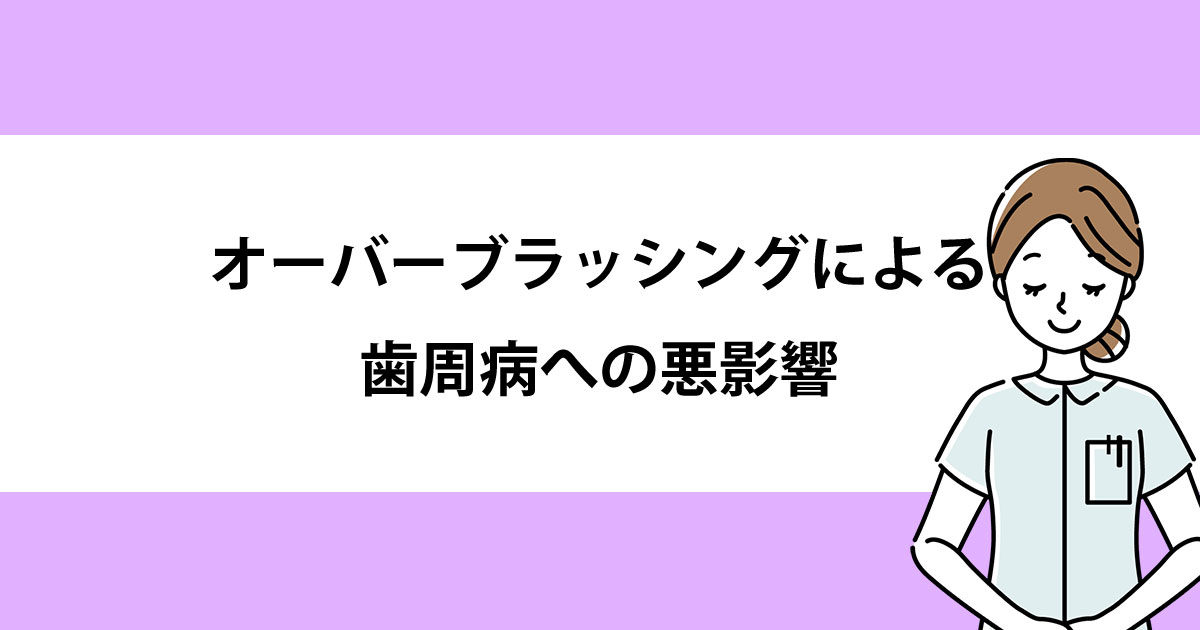
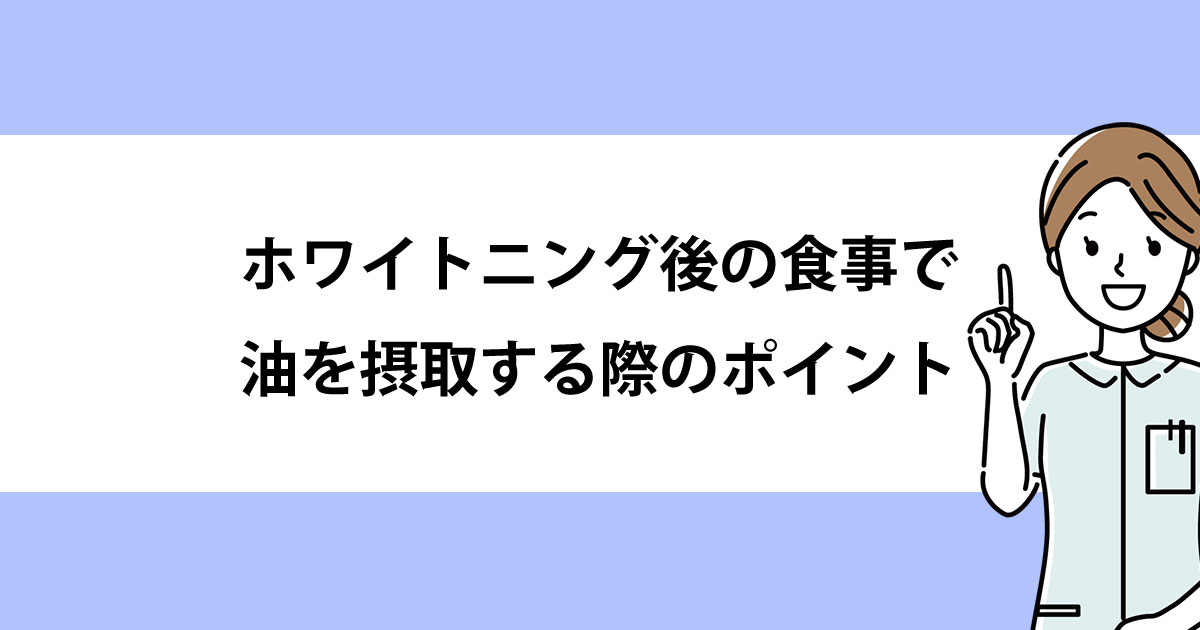
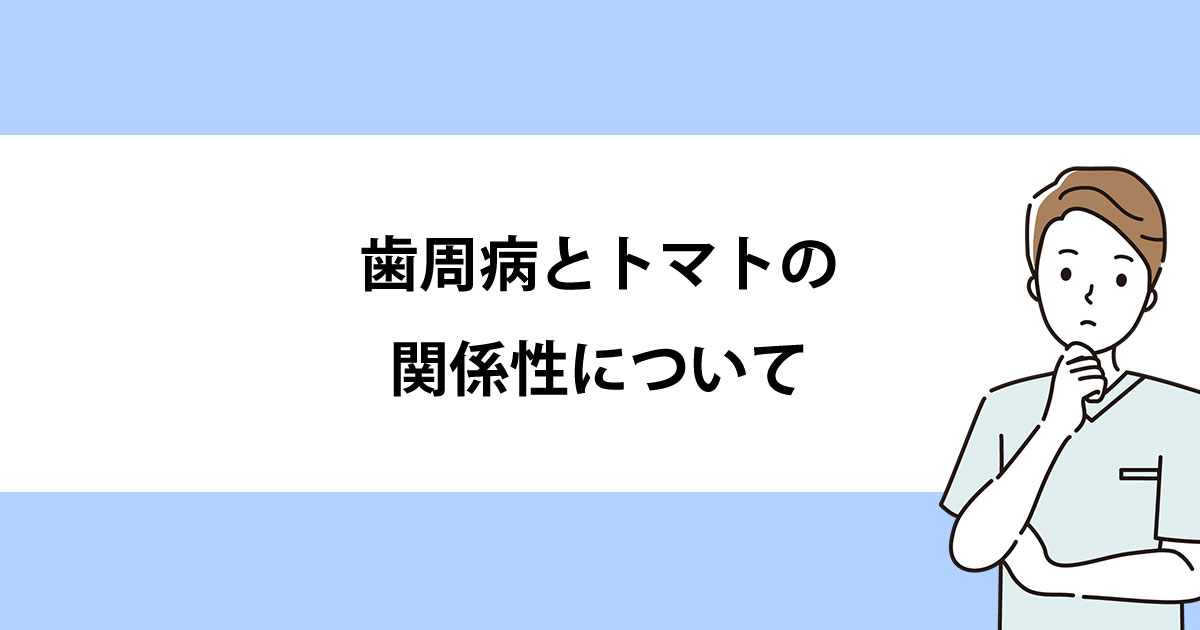
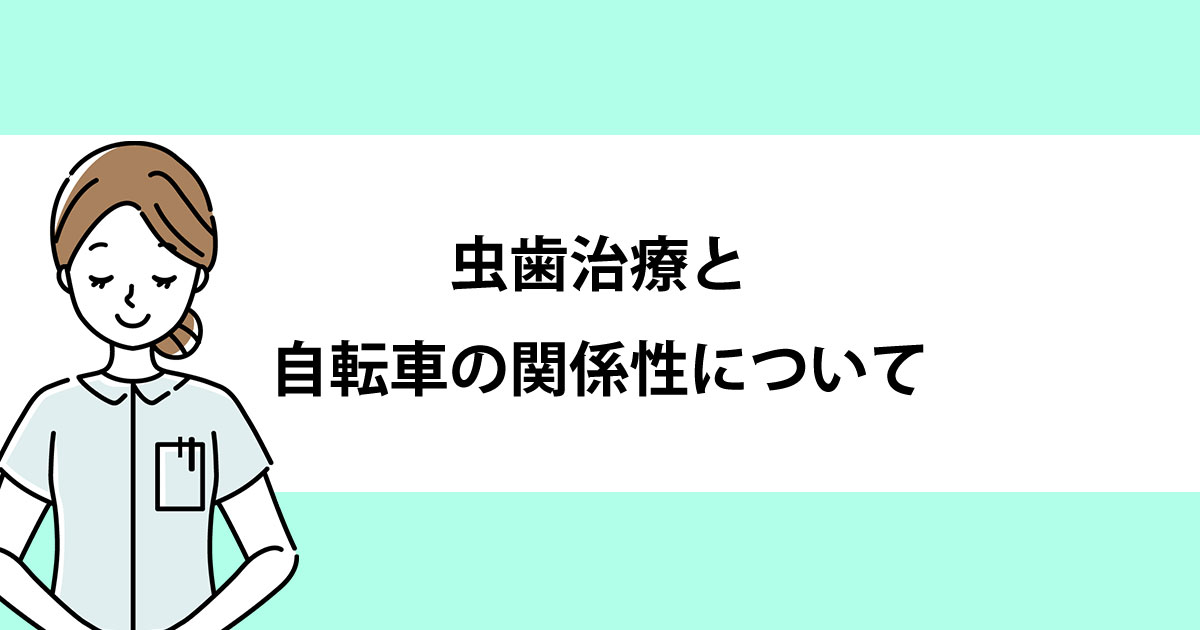
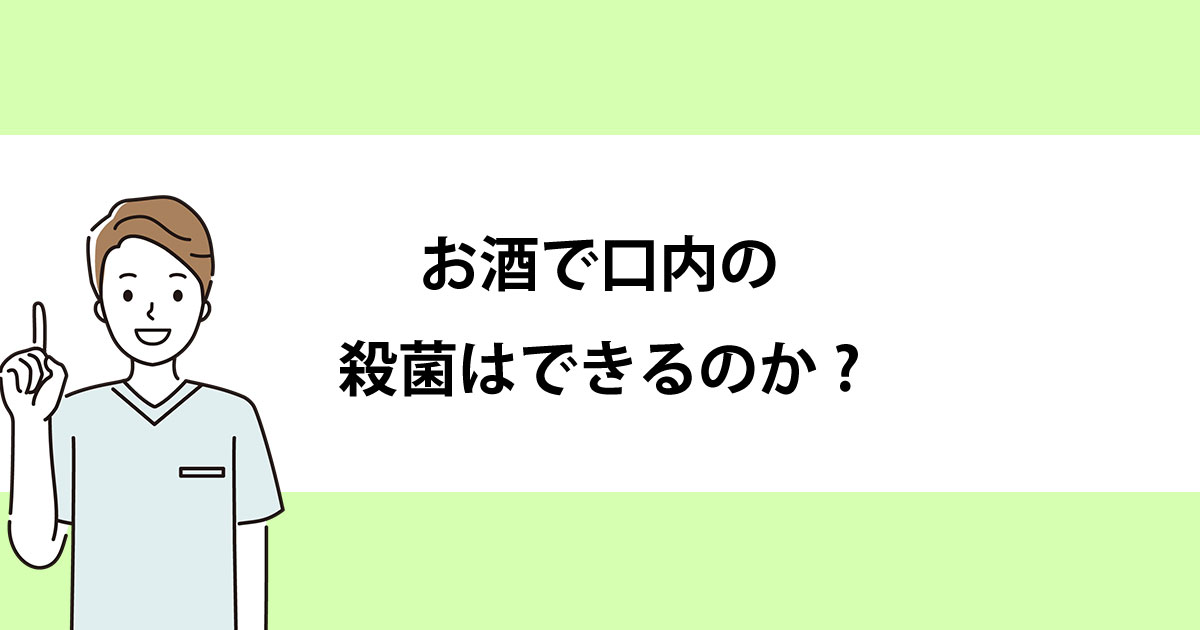



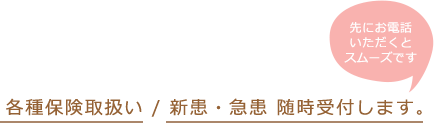

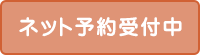
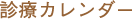






 TEL
TEL