日中、就寝中を問わず、無意識に歯ぎしりをしている方は少なからず存在します。
また歯ぎしりは、歯や顎などに負担をかけるだけでなく、虫歯のリスクを高める可能性もある疾患です。
そのため、できる限り早めに対処しなければいけません。
今回は、歯ぎしりが虫歯のリスクを高める仕組みについて解説します。
歯ぎしりの概要
歯ぎしりは、無意識のうちに歯をすり合わせたり、食いしばったりする行為です。
具体的には、グラインディングやクレンチング、タッピングというものが歯ぎしりに該当します。
グラインディングは、下顎を左右に動かし、歯をギリギリとこすり合わせる行為です。
音を伴うことが多く、周囲の方が気付くこともあります。
またクレンチングは、ストレスや緊張で上下の歯を強く噛みしめる行為です。
音はしないため、本人は自覚しにくい傾向にあります。
さらにタッピングは、上下の歯を小刻みにぶつけ、カチカチと音を立てる行為です。
原因はストレスなど精神的なものや、睡眠の質の低下などが考えられます。
歯ぎしりが虫歯のリスクを高める仕組み
歯ぎしりによって強い力がかかると、歯の表面を覆うエナメル質が擦り減ったり、目に見えない小さなヒビが生じたりします。
このようなヒビの隙間から、虫歯菌が歯の内部に侵入しやすくなります。
また歯ぎしりをすることで唾液の流れが悪くなり、口の中が酸性に傾きやすくなります。
酸性の環境は、虫歯の原因となる細菌が繁殖しやすい状態です。
ちなみに就寝中は、ただでさえ口内の唾液の分泌量が減少し、虫歯のリスクが高まります。
歯ぎしりの多くは睡眠中に行われるため、症状がひどいほど虫歯の発症につながりやすいです。
歯ぎしりの対処法
歯ぎしりの対処法としては、歯科クリニックでのマウスピース療法や噛み合わせの調整などが挙げられます。
マウスピース療法は、ナイトガードと呼ばれるマウスピースを装着し、歯や顎関節への負担を軽減するものです。
また不正な噛み合わせが原因の場合、詰め物や被せ物の高さを調整したり、矯正治療を行ったりすることである程度改善が見込めます。
この記事のおさらい
今回の記事のポイントは以下になります。
・歯ぎしりは、無意識のうちに歯をすり合わせたり、食いしばったりする行為
・歯ぎしりによって強い力がかかると歯に小さなヒビが生じ、虫歯菌が侵入しやすくなる
・歯ぎしりは唾液の流れを悪化させ、口内を虫歯菌が好む環境にしてしまう
・歯ぎしりの対処法にはマウスピース療法や噛み合わせの調整などがある
以上のポイントはしっかりと押さえておきましょう!
新潟市西区周辺やJR越後線「寺尾駅」付近で歯科クリニック(歯医者さん)をお探しの方は、是非、ひらの歯科医院へお問い合わせ下さい!
万全の感染予防対策でお待ちしております。






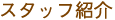

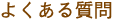
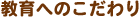
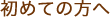






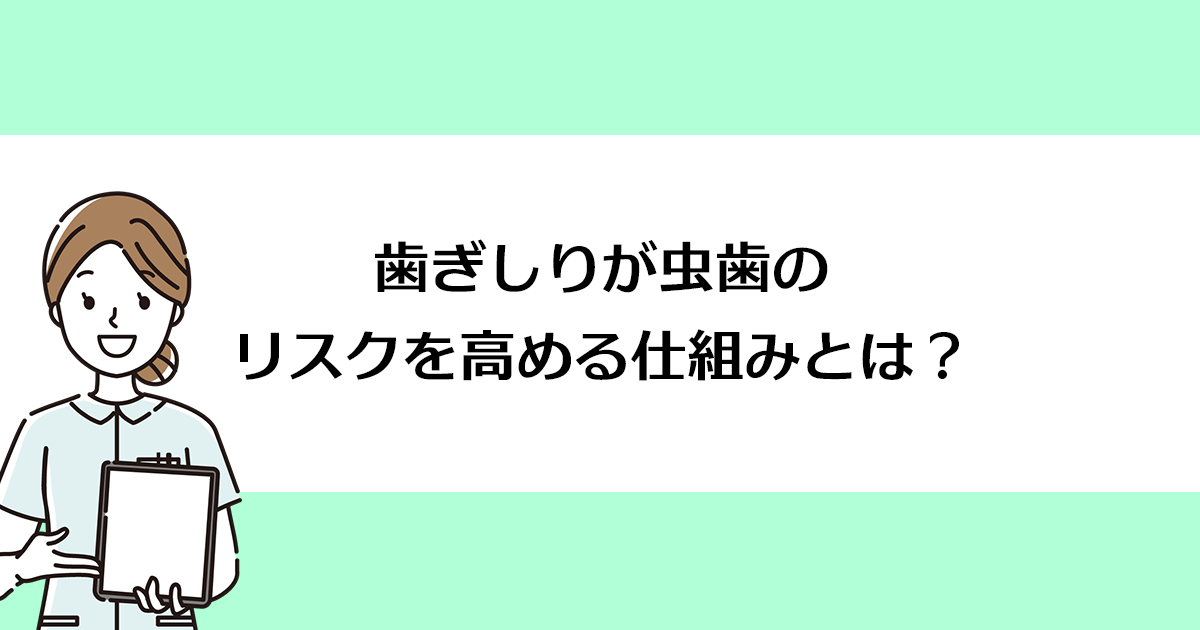



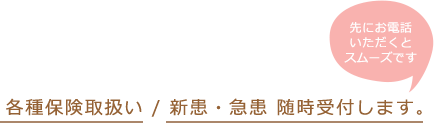

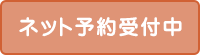
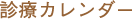






 TEL
TEL