肉類は、良質なタンパク質を摂取できるものであり、日々の食事において摂り入れなければいけないものの一つです。
また食事と関連性がある口腔疾患の一つに歯周病が挙げられますが、肉類の摂取と歯周病には一体どのような関係性があるのでしょうか?
今回はこちらの点について解説します。
歯周組織の健康維持につながる
冒頭でも触れたように、肉類は良質なタンパク質の供給源です。
そのため、摂取することで歯周組織の健康維持につながります。
歯茎や歯を支える骨などは、主にコラーゲンなどのタンパク質で構成されています。
タンパク質が不足すると、これらの組織の強度が低下し、歯周病の進行を助長する可能性があります。
肉類は良質なタンパク質源であるため、適量をバランス良く摂取することは、歯周病予防の一環として効果的です。
肉類の脂質には注意
一定の歯周病予防効果が期待できる肉類ですが、一方で注意点もあります。
例えばラードやベーコンなどに含まれる飽和脂肪酸、トランス脂肪酸といった質の良くない脂は、歯周病予防の観点からはなるべく摂取を控えるべきとされています。
逆に摂取すべきなのは、炎症を抑える働きのあるオメガ3脂肪酸で、こちらは魚介類やクルミなどに多く含まれるものです。
つまり、肉類中心で魚をあまり食べない食生活には注意しなければいけないということです。
硬い肉の摂取も控えるべき
ある程度歯周病の症状が出ている方は、歯茎が炎症を起こしている可能性が高いです。
またこのような状況の場合、硬い肉は歯茎に物理的な負担をかけ、炎症部位を悪化させる可能性があります。
そのため、鶏肉のようなやわらかい肉を選んだり、シチューや挽肉料理にしたりするなど、調理法を工夫することも大切です。
ちなみに、先ほど肉だけでなく魚も摂取しなければいけないという話をしましたが、当然野菜や果物の摂取も必須です。
肉類が多く野菜や果物が少ないという偏食パターンは、ミネラルやビタミン不足を引き起こし、歯周病になりやすい体質をつくることがあります。
さらに、歯茎の修復には、ビタミンCなどの栄養素が不可欠です。
この記事のおさらい
今回の記事のポイントは以下になります。
・肉類は良質なタンパク質の供給源であり、歯周組織の健康維持につながる
・飽和脂肪酸、トランス脂肪酸などの脂は、歯周病予防の観点からはなるべく摂取を控えるべき
・硬い肉は歯茎に物理的な負担をかけ、歯周病の炎症部位を悪化させる可能性がある
・歯周病を予防するには、魚類や野菜、果物などもバランス良く摂取する必要がある
以上のポイントはしっかりと押さえておきましょう!
新潟市西区周辺やJR越後線「寺尾駅」付近で歯科クリニック(歯医者さん)をお探しの方は、是非、ひらの歯科医院へお問い合わせ下さい!
万全の感染予防対策でお待ちしております。






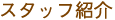

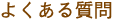
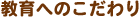
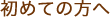






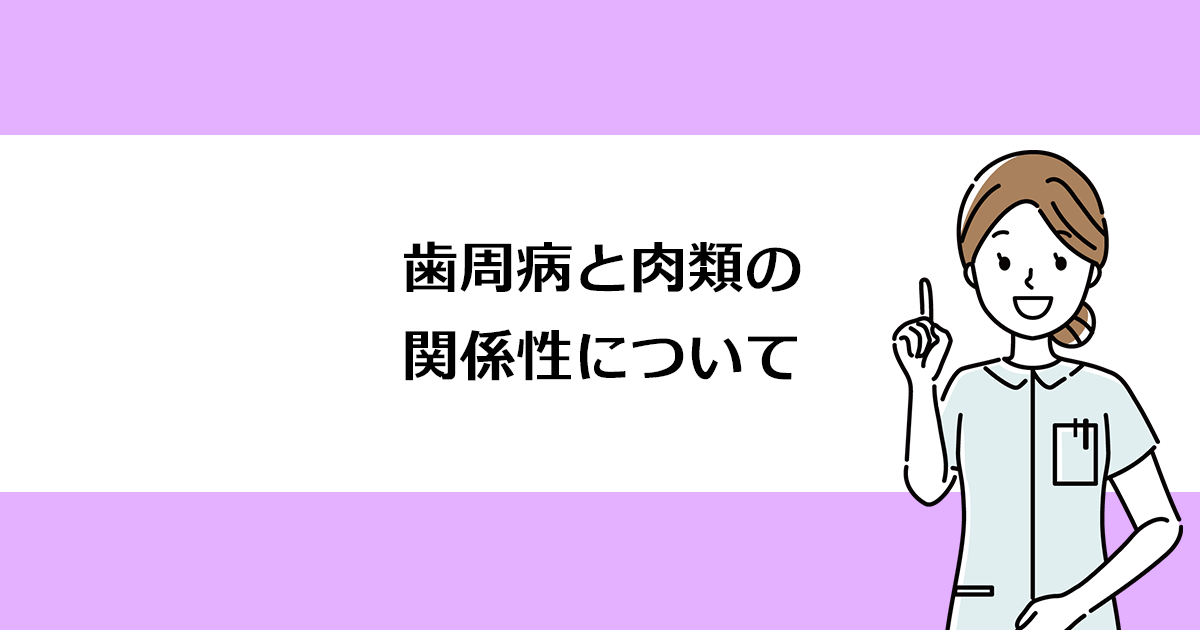



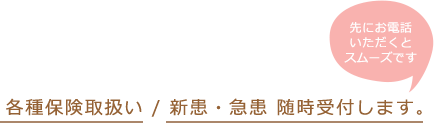

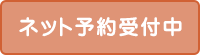
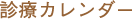






 TEL
TEL