虫歯がある程度進行している場合、食べ物を咀嚼したときの刺激で歯がズキッと痛むことがあります。
また飲み物に関しても、歯に触れたときにしみるような痛みが出ることが考えられます。
今回は、このような状況のとき、虫歯がしみるのを防ぐための飲み物の飲み方について解説します。
ストローを使用する
飲み物を飲むたびに虫歯が痛むという場合は、ストローを使用することをおすすめします。
こちらは飲み物が歯に触れにくくなるからです。
虫歯の痛みを発生させる飲み物は、大量の砂糖が含まれるような甘いジュースや、極端に冷たい飲み物などです。
ストローを使用すれば、これらが歯に触れる面積を少なくし、痛みを軽減しながら飲むことができます。
具体的には、ストローを口の奥の方でくわえることにより、直接喉に飲み物を入れるようなイメージです。
ただし、ホットコーヒーなど熱い飲み物は、ストローで飲むと火傷するためおすすめできません。
酸性の飲み物を避ける
虫歯がしみるのを防ぐためには、なるべく酸性の飲み物を避けるようにしましょう。
先ほど、虫歯がしみるのは甘いジュースや冷たいものという話をしました。
しかし、甘さや冷たさだけでなく、酸性かどうかも飲み物を選ぶ際の重要なポイントです。
例えば炭酸飲料やスポーツドリンクなどは酸性度が高く、歯のエナメル質を溶かしてしまうおそれがあります。
歯の表面を覆うエナメル質が溶けてしまうと、虫歯の本数がさらに増加し、飲み物を飲むときの痛みが増幅してしまうおそれがあります。
飲んだ後にすぐうがいをする
虫歯がしみるのを防ぐためには、飲み物を飲んだ後にすぐうがいをすることも大切です。
虫歯の痛みは、飲み物を飲んだ瞬間にだけ発生するわけではありません。
飲み物の成分が口内に残存し、口内環境が悪くなっている場合、持続的にズキズキと痛むことがあります。
そのため、特に酸性の飲み物や糖分が多い飲み物を飲んだ後は、水で口をすすぐことで口内環境を清潔に保ち、歯への影響を軽減しなければいけません。
もちろん、口内をすすぐときに使用する水は、ぬるま湯程度のものが望ましいです。
この記事のおさらい
今回の記事のポイントは以下になります。
・虫歯がしみるときは、飲み物が歯に触れる面積を減らすためにストローを使用するのがおすすめ
・炭酸飲料やスポーツドリンクは酸性度が高く、虫歯の症状を悪化させてしまう可能性がある
・飲み物を飲んだ後すぐにうがいをすれば、成分が口内に残ってしみるのを防ぎやすくなる
以上のポイントはしっかりと押さえておきましょう!
新潟市西区周辺やJR越後線「寺尾駅」付近で歯科クリニック(歯医者さん)をお探しの方は、是非、ひらの歯科医院へお問い合わせ下さい!
万全の感染予防対策でお待ちしております。






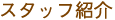

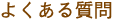
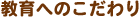
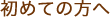






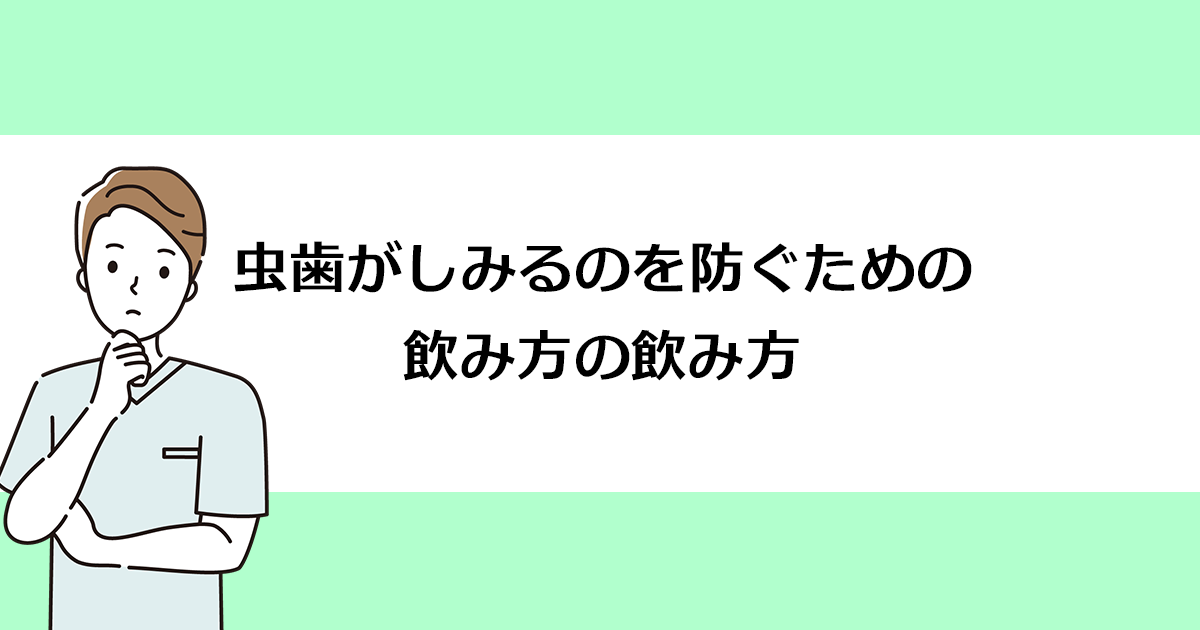
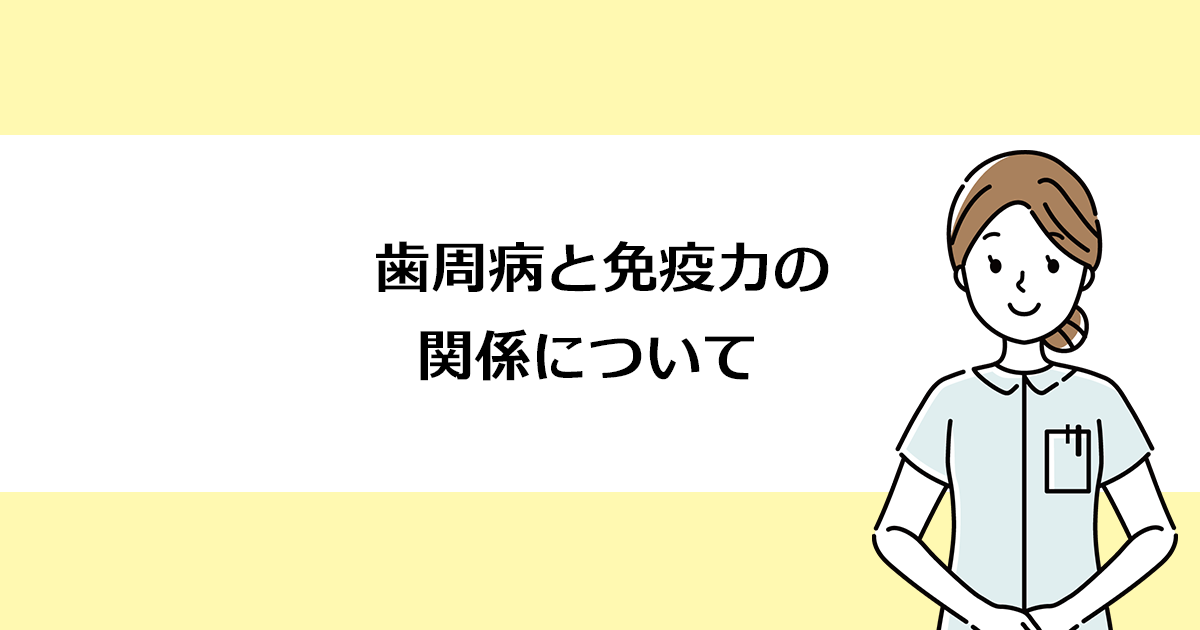
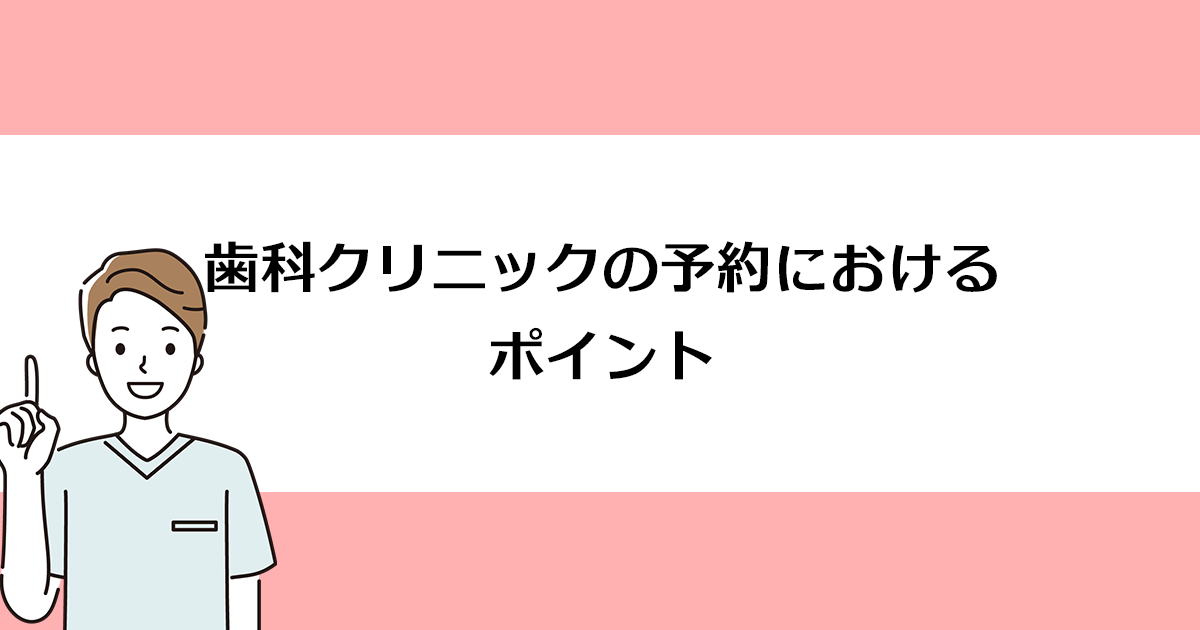
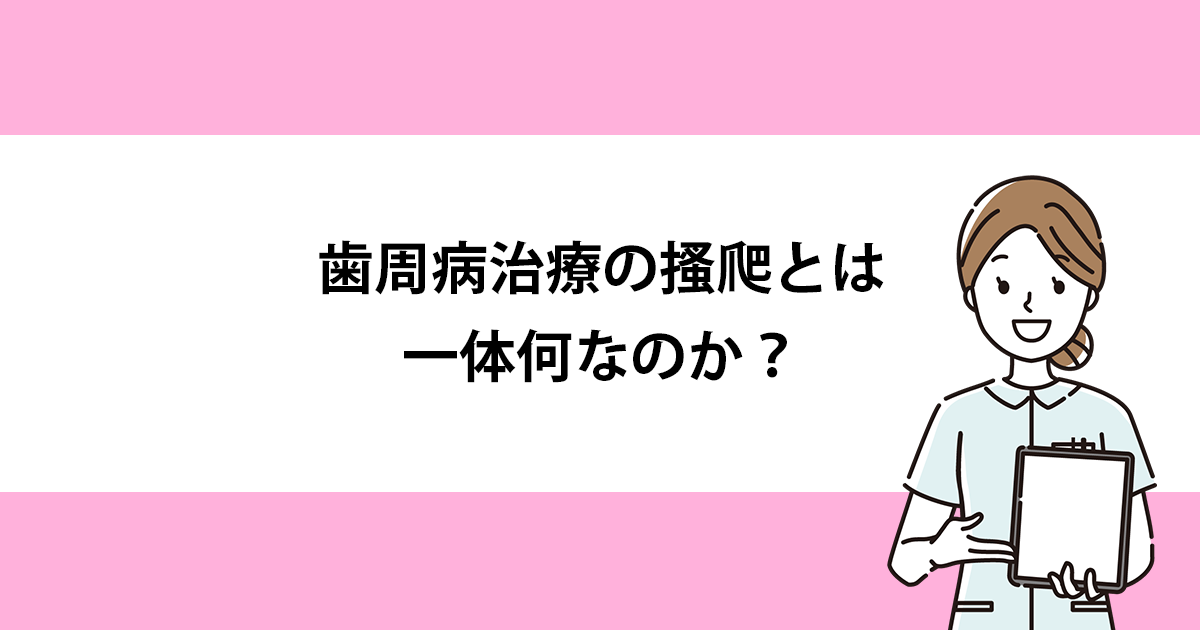

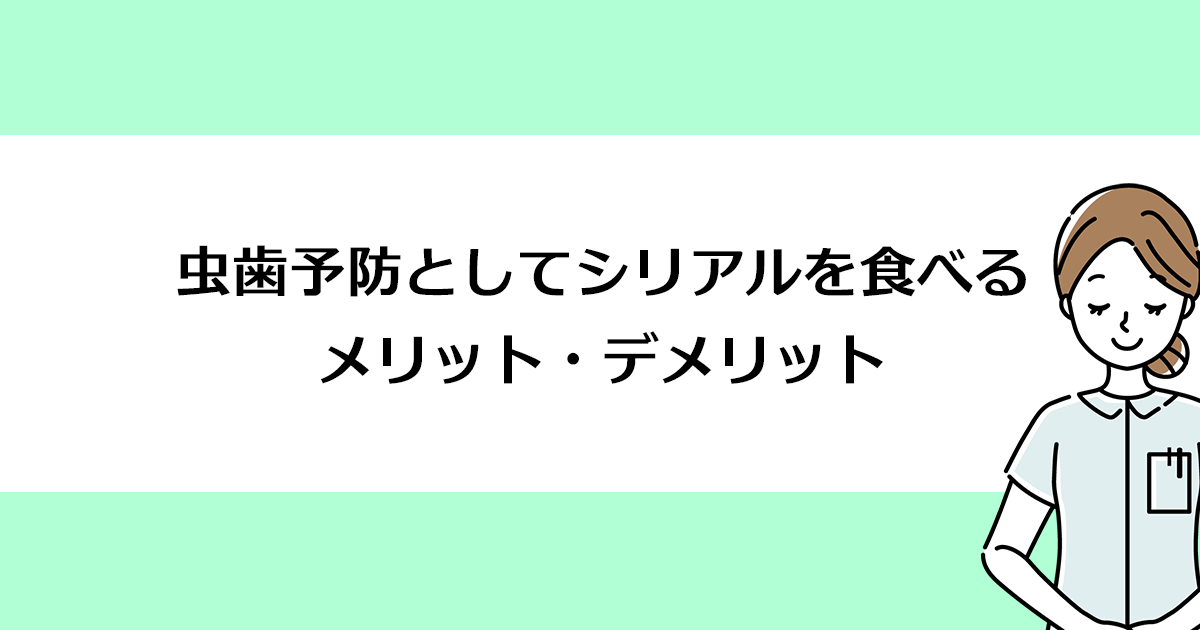
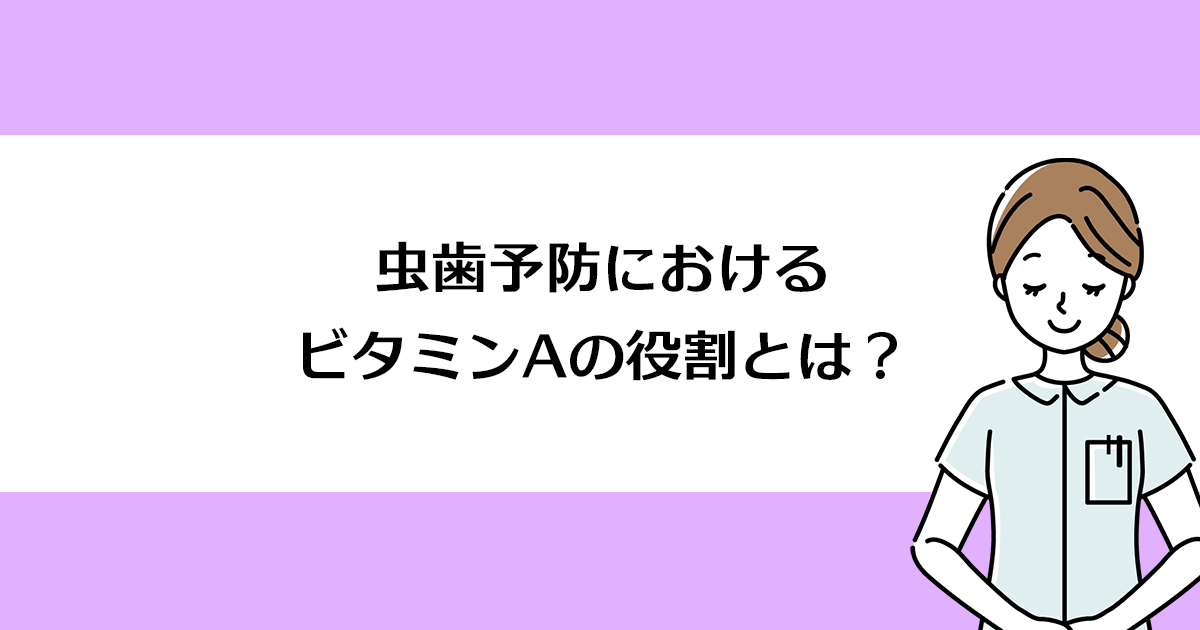
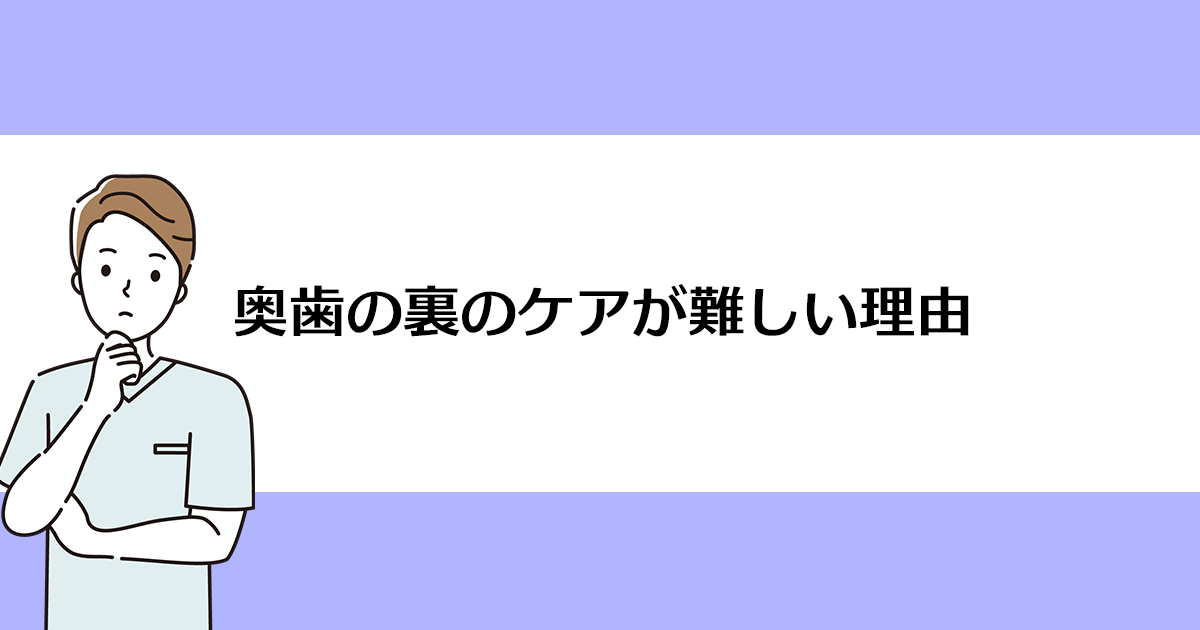
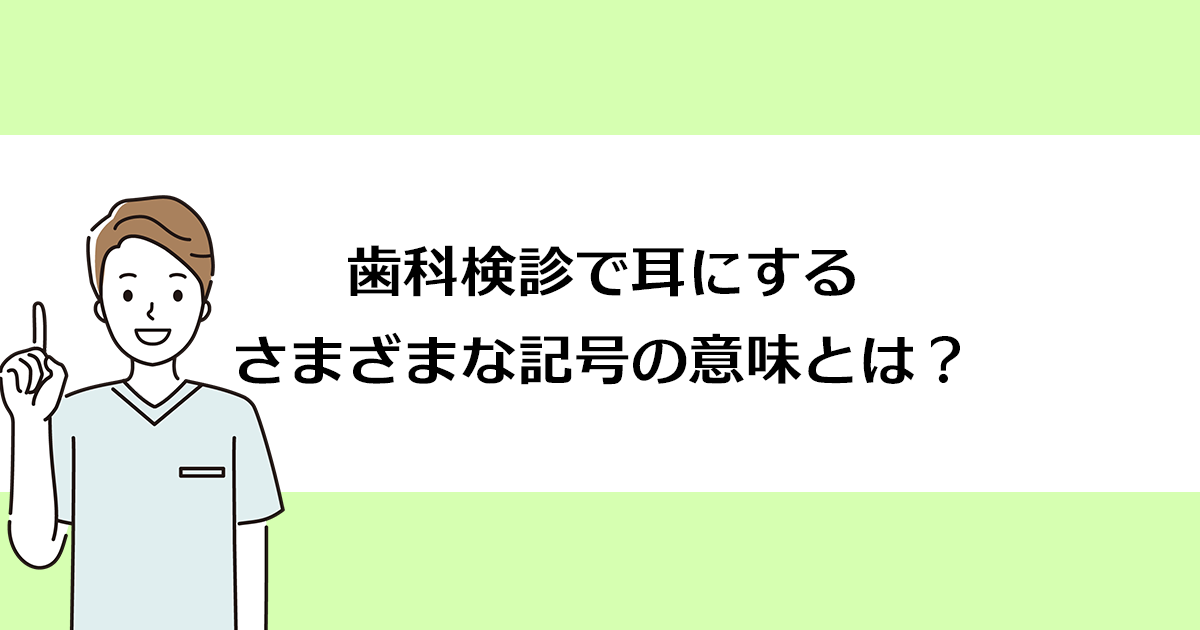
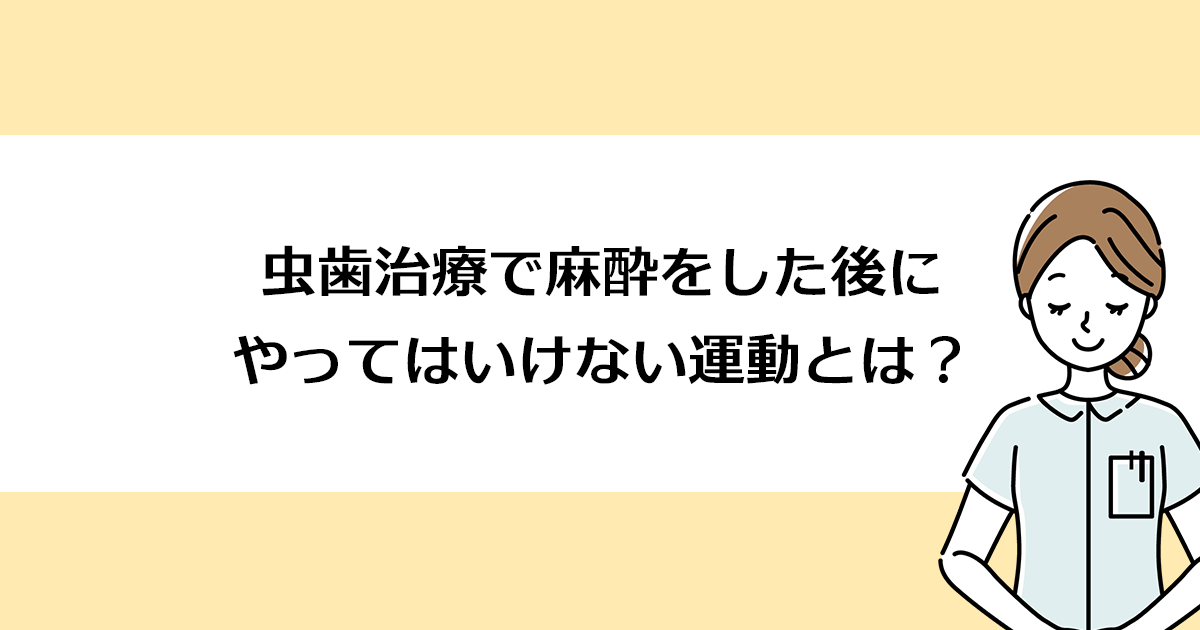



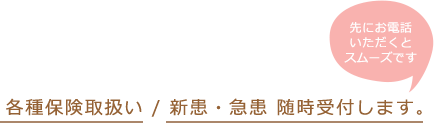

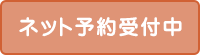
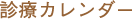






 TEL
TEL