歯周病は、数ある疾患の中でもっとも気を付けなければいけない疾患と言っても過言ではありません。
なぜなら、世界一感染者数が多い感染症として、ギネス記録に認定されているからです。
また抗てんかん薬を服用している方は、特に歯周病に注意すべきだと言えます。
今回はこちらの点について解説します。
抗てんかん薬の概要
抗てんかん薬は、脳の神経細胞の過剰な電気的興奮を抑え、てんかん発作を予防・軽減する薬です。
てんかんの種類や発作のタイプ、患者さんの年齢や状態に合わせて、さまざまな種類の抗てんかん薬が処方されます。
また抗てんかん薬には眠気やふらつき、吐き気や消化器症状、皮膚症状といった副作用が起こる可能性があります。
そのため、てんかんの発作がある方にとっては必需品ですが、慎重に使用しなければいけないものでもあります。
歯周病と抗てんかん薬の関係
抗てんかん薬の服用は、さまざまな副作用を引き起こすという話をしました。
そのうちの一つに、歯茎の腫れが挙げられます。
こちらは薬物性歯肉増殖症と呼ばれるもので、歯茎の腫れは歯周病の原因菌の温床となりやすく、歯周病の進行を早める可能性があります。
特に、フェニトインと呼ばれる抗てんかん薬は、歯肉増殖のリスクが比較的高いことで知られています。
フェニトインを長期服用した方の50%以上の方は、歯茎の腫れを引き起こしているというデータもあるくらいです。
しかし歯茎が腫れるからといって、てんかんの発作がある方は簡単に薬の服用を中止するわけにはいきません。
てんかんの患者さんの歯周病対策
てんかんの患者さんは、抗てんかん薬の作用により、歯周病が悪化しがちです。
そのため、より丁寧なブラッシングやフロスなどによるプラークコントロールが求められます。
またてんかんを持つ方は、発作や身体的な制限により、口腔ケアが不十分になりがちです。
こちらのケア不足を補うためには、自宅でのセルフケアだけでなく、歯科クリニックで定期的なメンテナンスを受けることも大切です。
ちなみに薬の変更や歯茎の腫れに対する他の治療法については、歯科医師だけでなく内科の主治医に相談することが望ましいです。
この記事のおさらい
今回の記事のポイントは以下になります。
・抗てんかん薬は、脳の神経細胞の過剰な電気的興奮を抑え、てんかん発作を予防・軽減する薬
・抗てんかん薬を服用する方は、薬物性歯肉増殖症という副作用が起こることがある
・特にフェニトインと呼ばれる抗てんかん薬は、歯肉増殖のリスクが比較的高い
・てんかんの患者さんは、より歯周病予防を徹底する必要がある
以上のポイントはしっかりと押さえておきましょう!
新潟市西区周辺やJR越後線「寺尾駅」付近で歯科クリニック(歯医者さん)をお探しの方は、是非、ひらの歯科医院へお問い合わせ下さい!
万全の感染予防対策でお待ちしております。






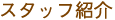

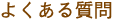
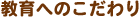
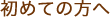






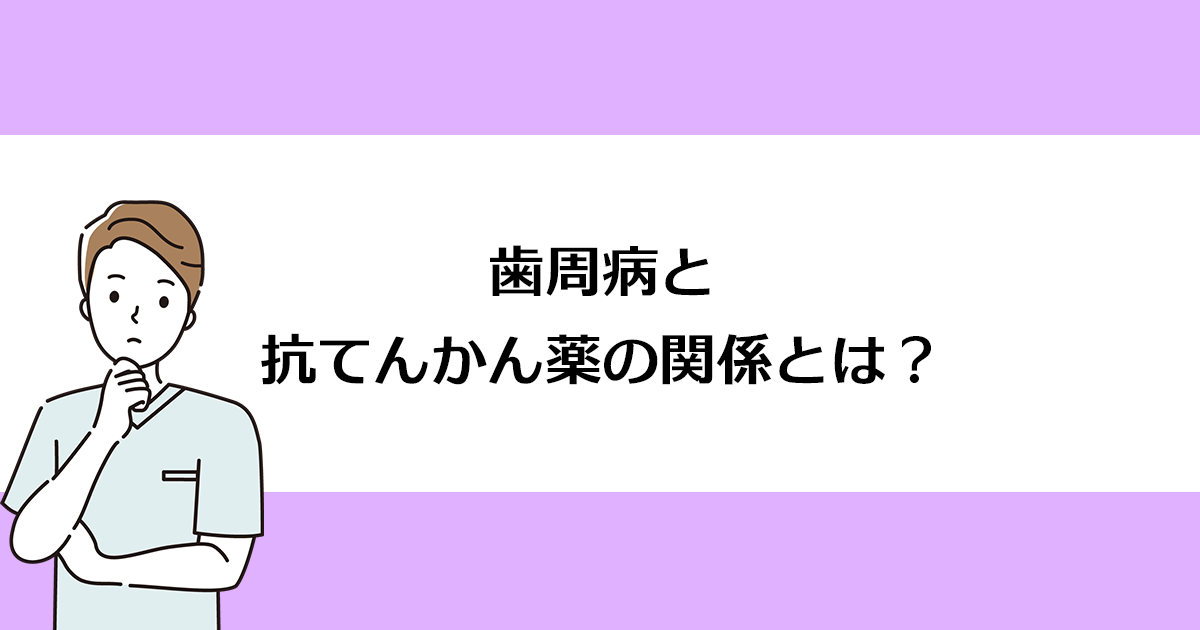



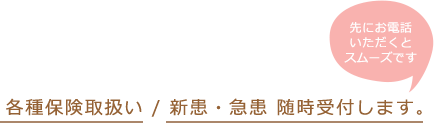

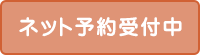
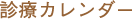






 TEL
TEL