歯周病は、不十分な口内ケア、糖分の摂取といった原因で増加した歯周病菌などの細菌感染により、歯茎や骨などに悪影響を及ぼす病気です。
また、歯周病には軽度、中度、重度が存在し、それぞれに見られる症状は異なります。
ここからは、各段階における歯周病の主な症状について解説したいと思います。
●軽度歯周病の症状について
歯周病は、“サイレント・ディジーズ(静かなる病気)”とも呼ばれるほど、なかなか発症していることに気付かない病気です。
特に、軽度の歯周病は、それほど重大な症状が出ないため、気付かない方も多いです。
そのため、以下のような症状が少しでも見られる場合は、「痛みもないし大丈夫だろう」と放置せず、早急に歯科クリニックに相談してください。
・歯茎が赤っぽく腫れる
・歯磨きや食事の際、出血することがある
・冷たい水がしみることがある
・歯を押すと少し前後に動くことがある
●中度歯周病の症状について
中度の歯周病まで進行すると、歯周ポケットが4~6mmほどの深さにまで達します。
ここまで進行すると、歯周ポケットの奥までしっかりとブラッシングをするのは困難になり、プラークや歯石はますます溜まってしまいます。
また、中度の歯周病において見られる症状としては、主に以下のことが挙げられます。
・歯茎の腫れがひどく、ブヨブヨしている
・頻繁に歯茎から出血する
・歯周ポケットから膿が出ることがある
・口臭がする
・歯茎が下がり、歯が長くなったように見える
・歯が前後左右にグラつく
・硬いものを噛んだときに違和感や痛みがある
●重度歯周病の症状について
歯周病が重度にまで進行すると、歯周ポケットの深さは6mmを超え、歯槽膿漏と呼ばれる状態になります。
歯を支える顎の骨は大幅に溶かされ、歯が抜けてしまうリスクも高まるため、こちらの段階にいくまでに歯科クリニックで治療を行い、阻止しなければいけません。
また、重度の歯周病における主な症状としては、以下のことが挙げられます。
・歯茎が真っ赤に腫れ、膿が出る
・歯周ポケットからの出血がひどくなる
・歯の激しいグラつき、食事の不自由さを感じる
・歯と歯の隙間が極めて大きくなる
・強烈な口臭がする
●この記事のおさらい
今回の記事のポイントは以下になります。
・歯周病は“サイレント・ディジーズ(静かなる病気)”と呼ばれるほど気付きにくい病気
・特に軽度の歯周病は症状が出にくく、気付かない人も多い
・中度の歯周病になると歯周ポケットが深くなり、プラークや歯石が溜まりやすくなる
・重度の歯周病は顎の骨を溶かし、歯が抜けるリスクも高まる
以上のポイントはしっかりと押さえておきましょう!
新潟市西区周辺やJR越後線「寺尾駅」付近で歯科クリニック(歯医者さん)をお探しの方は、是非、ひらの歯科医院へお問い合わせ下さい!
万全の感染予防対策でお待ちしております。






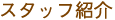

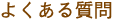
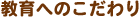
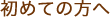




















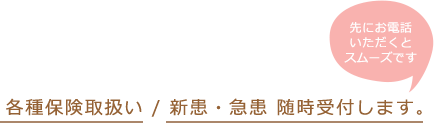

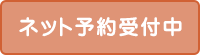
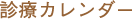






 TEL
TEL